『風の谷のナウシカ』の中で一度聴いたら忘れられない印象的なメロディ、「ランランララ~♪」。
セリフもなく繰り返されるこの歌が、なぜ多くの人の記憶に残っているのでしょうか?
この記事では、その正体・意味・使用されているシーン・作曲者までを徹底的に解説し、ナウシカの世界観をより深く味わうヒントをお届けします。
この記事を読むとわかること
- 「ランランララ~♪」の正式名称と作曲者
- 劇中で使われている場面と演出意図
- 言葉を超えた音楽のメッセージ性と海外での反響
「ランランララ~♪」の曲名と作曲者は?
映画『風の谷のナウシカ』の中で、観客の心に深く刻まれるのが、あの特徴的な旋律「ランランララ~♪」です。
その正体を知らずに口ずさんでいる人も多いですが、この曲には明確なタイトルと作曲者が存在します。
本項では、その曲の正式名称と制作の背景をひも解いていきます。
正式タイトルは「王蟲との交流」
実はこの曲の正式なタイトルは、「王蟲との交流」です。
劇中ではナウシカが王蟲の幼生と心を通わせる重要な場面で使われており、言葉を使わずに感情を伝え合う“共鳴”の象徴として機能しています。
メロディに歌詞はなく、「ランランララ~」というスキャット(擬声)によって構成されているため、観客の印象には“歌”として強く残るのです。
作曲は久石譲、“声”はコーラスユニット
この劇中音楽を手がけたのは、スタジオジブリ音楽の常連である久石譲氏。
シンプルながらも印象的な旋律と、柔らかく透き通るような女性コーラスの融合によって、自然と人間が静かに心を通わせる“優しい空間”が表現されています。
歌っているのは、久石譲作品でたびたび起用されるコーラスユニット「杉並児童合唱団」やスタジオボーカルとされています(正式クレジットは未公開)。
言語を持たない声の響きが、まるでナウシカと王蟲の心の会話そのもののように感じられ、観客の感情を揺さぶります。
そのため、「ランランララ~♪」という旋律は、単なるBGMではなく、物語の感情を導く“もうひとつのセリフ”とも言えるのです。
どのシーンで流れている?
「ランランララ~♪」という旋律が強く印象に残る理由のひとつは、その音楽が使用されたシーンの演出が極めて美しいことにあります。
この曲はただBGMとして流れているのではなく、ナウシカと王蟲の“心の交信”を音楽で表現する場面で登場し、物語の感動を高めています。
王蟲の幼生をナウシカが導く名場面
この音楽が最も印象的に流れるのは、ナウシカがペジテの人々に囚われた王蟲の幼生を解放し、自らの命をかけて群れのもとへと導くシーンです。
血まみれになった幼い王蟲の叫びに応えるように、ナウシカは自分の身を投げ出し、王蟲たちの怒りを鎮めようと歩み寄っていきます。
その時、画面全体が金色の光に包まれ、「ランランララ~♪」という旋律が静かに流れ始めるのです。
このシーンは、ナウシカが“選ばれし者”として覚醒する瞬間であり、王蟲との完全なる心の調和が描かれています。
緊張と癒しが共存する絶妙な演出
この楽曲が流れる場面は、物語上、極度の緊張と感動が交錯するクライマックスです。
無数の王蟲が押し寄せるという破滅的な状況の中、ナウシカの“赦し”と“祈り”が、静かに世界のバランスを取り戻していく――
そこに添えられる「ランランララ~♪」のスキャットは、ナウシカの優しさと王蟲の感情が溶け合う“音の祈り”のように響きます。
このように、本楽曲は視聴者の感情を導く“サウンドトラック”としてだけでなく、ナウシカというキャラクターの魂を象徴する音楽として、物語に欠かせない存在となっているのです。
「歌詞がないのに印象的」な理由とは?
「ランランララ~♪」という旋律は、言葉のないスキャットで構成されているにもかかわらず、多くの人の心に強く残る名曲です。
この“無言の歌”がなぜここまで印象深いのか、その秘密は音の構造と感情の共鳴にあります。
ここでは、その印象深さの理由を、音楽的・感情的な観点から掘り下げていきます。
声の響きが生む“原始的な感情の共鳴”
この楽曲は明確な歌詞を持たず、「ランランララ~」という音の連なりだけで構成されています。
しかしその響きは、母親が子守唄を口ずさむような、非常にプリミティブ(原始的)な感覚を呼び起こします。
言語よりも前にある“声そのもの”が持つ力が、聞き手の潜在意識に直接働きかけ、深い安心感や共鳴を生み出しているのです。
この効果によって、観客はナウシカの感情や王蟲たちの静かな変化を、「理屈ではなく感覚」で受け取ることができます。
言葉を超えたメッセージ性
『風の谷のナウシカ』の物語には、「言葉を交わさなくても理解できる」存在との出会いが繰り返し描かれます。
腐海の生き物、王蟲、蟲たち、さらには自然そのもの――ナウシカはそうした存在と“沈黙の対話”を交わしていきます。
「ランランララ~♪」のスキャットもまた、その対話を音楽として可視化したものだと言えるでしょう。
言葉を使わないこの楽曲は、観る者に“意味を押しつけない自由”を与えます。
それぞれが自分の感情や記憶に重ねてこの旋律を受け取ることができる――それこそが、この曲が“記憶に残る歌”となった最大の理由なのです。
海外ではどう受け止められている?
「ランランララ~♪」という劇中歌は、日本だけでなく海外でも多くの視聴者に強い印象を残しています。
特に英語圏のジブリファンの間では、“言葉を超えた音楽体験”として評価されており、SNSやレビューサイトでもたびたび言及されています。
ここでは、海外でこの楽曲がどのように受け止められているかを見ていきます。
英語圏でも「La La La Song」として話題に
この曲は公式には「王蟲との交流(The Encounter with Ohmu)」とクレジットされていますが、ファンの間では「La La La Song」や「Nausicaä Chant」といった呼び名で親しまれています。
YouTubeやRedditなどの海外ファンフォーラムでは、「この曲を聴くと涙が出る」「ナウシカの本質を音で語っている」といった声が多数見受けられます。
英語の歌詞がなくても伝わる感情の深さが、言語を越えて支持されている理由のひとつです。
“癒しのテーマ”として評価される理由
この旋律は、多くの海外リスナーにとって、“心を落ち着ける癒しの音楽”として受け入れられています。
特にジブリ音楽を収録したヒーリングアルバムやローファイミックスでは、この曲が定番のように収録されており、静かな夜のBGMとして好まれる傾向があります。
「自然」「優しさ」「祈り」などのキーワードと結びつくこの曲は、ナウシカの精神性を凝縮した“音の象徴”として、多くの人々の心に寄り添っているのです。
このように、「ランランララ~♪」は日本だけでなく、世界中の人々に静かな感動を与え続けている名曲であることがわかります。
「ランランララ~♪」が象徴するナウシカの世界観まとめ
「ランランララ~♪」というスキャットの旋律は、単なる劇中BGMではありません。
それは『風の谷のナウシカ』の根底に流れるテーマ――自然との共生、言葉を超えた理解、命の尊厳――を音楽という形で体現する存在です。
その静かな響きは、観る者に多くを語らずして、本質的な“何か”を深く訴えかけてきます。
自然との共生と、言葉を超えた対話
ナウシカが王蟲の幼生に寄り添い、声を使わずに想いを伝えるシーン。
そこに流れる「ランランララ~♪」は、自然と人間が心を交わす瞬間を象徴しています。
言語が通じない存在との調和、怒りを鎮める優しさ、命の重みを分かち合う時間――それらすべてが、この音楽に詰まっているのです。
久石譲の音楽が導く“祈りの時間”
久石譲氏が描く音楽は、物語を補うのではなく、物語と一体化し、時には感情そのものを語る力を持っています。
「ランランララ~♪」は、言葉では伝えきれない祈りや願いを静かに響かせ、観る者の内面とゆっくり共鳴していくような音楽です。
それは、戦いや混乱の中にあっても決して失われてはならない、“心の静けさ”や“希望”を象徴しているのかもしれません。
「ランランララ~♪」は、ジブリ音楽の中でも特に言葉を超えて語りかけてくる一曲。
その旋律に耳を傾けたとき、私たちはナウシカの心、そして自然の声にそっと寄り添うことができるのです。
この記事のまとめ
- 「ランランララ~♪」の正式曲名は「王蟲との交流」
- 作曲は久石譲、スキャットで構成される
- 王蟲との共鳴シーンで使用される印象的な旋律
- 言葉を超えて感情を伝える“音の対話”
- 海外でも「癒しの音楽」として高く評価
- ナウシカの優しさと祈りを象徴する一曲
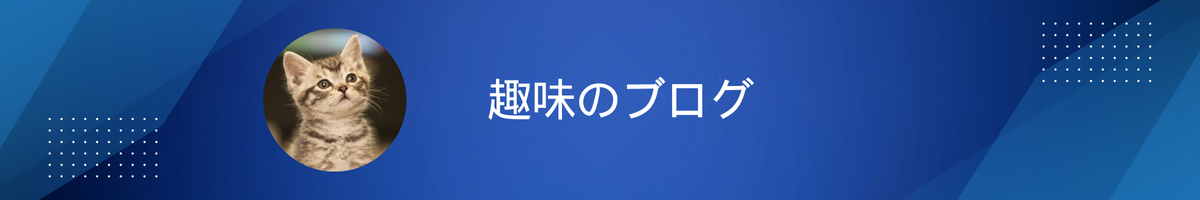

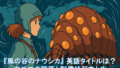

コメント